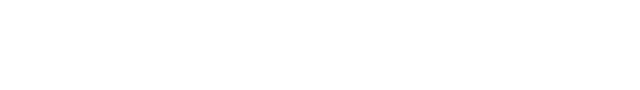パーキンソン病
パーキンソン病とは
神経内科疾患の中で、パーキンソン病は最も有名な病名の一つであり、誰でも一度はこの病名を聞かれたことがあるでしょう。「難病で、寝たきりになってしまう恐ろしい病気」といったイメージを持たれてしまいがちですが、本当は、この病気は神経内科疾患の中で、一番研究が進んでいて、治療薬もたくさんあって、手術まで出来るようになった病気です。
大切なことは、パーキンソン病に似ているけれど、違う病気をしっかり区別することと、その上で先々まで考えた治療計画を立てることであり、経験豊富な専門医に、納得できるまで相談しましょう。
パーキンソン病
中年期以降に発病し、手足がふるえたり、動作が緩慢になったり、歩くときに前傾姿勢になって、転びやすくなったりします。脳の中心部にある中脳の黒質と呼ばれる場所の神経細胞が減少し、脳内のドパミンという物質が減ることによって、症状が現れることがわかっています。
治療:たくさんの治療薬があり、レボドパという種類の薬がとてもよく効きますが、長年服用していると、いろいろな副作用が出てくることもあります。担当医と話し合いながら、それぞれの状況に最適な治療法を探して行きましょう。
パーキンソン症候群
多系統萎縮症、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症などが挙げられます。これらの病気は、パーキンソン病の症状以外の様々な症状が合併することで診断されますが、初期には区別することが難しいこともよくあります。
治療:パーキンソン病に準じた治療を行いますが、病気によって注意しなければならないことがあります。専門医とよく相談しましょう。
薬剤性パーキンソニズム
うつや食欲低下などに対して使われる薬で、パーキンソン病のような症状が見られることがあります。パーキンソン病自体の症状が、うつと間違われて、処方された薬で悪くなってしまうこともあります。
治療:原因となった薬をやめたり、他の薬に替えたりすることで改善します。
“つつみメモ”
・「手足の動かしにくさ」や「動作がゆっくりになった」という主訴では、原因としてパーキンソニズムを考える必要がある。
・漠然とした主訴の場合でも、入室時や病歴聴取時の観察によりパーキンソニズムを疑うことができる。全体的な動作の緩慢さがあるかどうか、目標到達地点である椅子のところに近づいていく際に小刻み歩行になっていないかどうか、歩行の際の姿勢が前傾姿勢かどうか、腕の振りが小さくなっていないかどうか。
・筋力低下との鑑別は、あまり力自体は使わない細かな動作がやりにくくなっていないかどうか、を確認していく。納豆をかき混ぜたり、卵をとくような動作がやりにくくなっていないか、衣服のボタンがかけにくくないか。
・小脳性運動失調との鑑別という点では、書字に注目する。パーキンソニズムがある場合には字が小さくなる(小字症)のに対して、小脳性運動失調ではトメ、ハネがやりづらく、速く書こうとすると字が汚くなる様子がみられる。
・急性から亜急性の経過では、薬剤性のパーキンソニズムを念頭に、内服薬について慎重に確認していく。
・慢性の経過で、全身性・両側性に症候がある場合には、パーキンソニズムをきたす変性疾患と考えられる。頻度が高いことと抗パーキンソン病薬が有効であることから、まずパーキンソン病を念頭に非運動症状(レム睡眠行動異常症、嗅覚低下、便秘、過活動膀胱、起立性低血圧など)の病歴確認も行う。パーキンソン病との鑑別が必要なパーキンソニズムを呈する神経変性疾患である非定型パーキンソニズムとして、多系統萎縮症、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症などがある。
・指タッピング(finger tapping)、つま先タッピング(toe tapping):パーキンソン病では、振幅の減衰傾向(繰り返していくうちに徐々に振幅が小さくなっていく)やタッピングの中断(すくみ)がみられるのに対し、進行性核上性麻痺では振幅が最初から小さいものの、減衰はみられないという特徴がある。
・筋強剛:四肢に加えて頸部、体幹もみていく。パーキンソン病の運動症状には左右差がみられることが多く、初診時から左右差があって、経過を通じてその左右差が維持される。進行性核上性麻痺では、四肢に比較して頸部や体幹の筋強剛が目立つ。脳血管性パーキンソニズムや特発性正常圧水頭症では上肢の症候が目立たず、歩行や下肢の症候が主体となるため、lower-half parkinsonismと称されることもある。
・指鼻指試験、指追い試験:上肢の小脳性運動失調を評価する診察法。これらの試験では、測定障害、とくに指が目標より行き過ぎてしまう測定過大があるかどうか、運動分解(指が目標に向かって一直線に滑らかに動かず、2相性あるいは多相性にカクカク、ギクシャクした動きになる)があるかどうかを観察していく。測定過大がある場合、目標に到達する際に、測定過大に対する修正の動きが混じり、指先が動揺する動き(終末時動揺、terminal oscillation)もみられる。測定障害は、動作がゆっくりだと検出しにくくなるため、評価時には被検者の動作スピードに注意する必要があり、パーキンソニズムを伴っている場合には小脳症候が評価しにくくなることに注意する。
・MIBG心筋シンチグラフィにおける心臓のMIBG集積低下は、パーキンソン病を含めたレヴィ小体蓄積がみられる疾患の診断に感度、特異度が高い。
・慢性経過で、L-dopa反応性不良のパーキンソニズムに加えて自律神経障害を伴う場合にはMSA-Pを考慮する。MSA-Pで認められるMRIのT2強調像における被殻外側縁の線状高信号化は、背側(後方)優位、非連続性、幅が不均一、被殻の萎縮や内側の低信号化を伴うという特徴がある。
・神経精神SLE(neuropsychiatric SLE:NPSLE)では、亜急性の経過でパーキンソニズムや傾眠傾向をきたし、MRIではT2強調像やFLAIR像で両側線条体や視床に高信号病変を認め、線条体脳炎の像を呈することがある。抗NMDA受容体抗体脳炎や抗LGI1抗体脳炎といった自己免疫性脳炎と鑑別を要する。