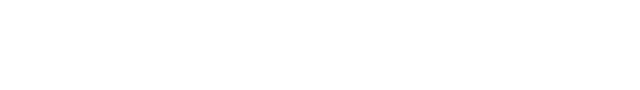歩きにくい
歩行困難
私たちは日常生活の中で、何気なく「歩く」という動作を行っていますが、その動作は、脳・脊髄・末梢神経・筋肉といった、運動に関わるすべての組織が、完璧に機能して初めて可能となります。
逆に言えば、歩きにくいということは、これらの組織のどこかに問題があるということです。
65歳以上の3万4485人を対象とした平均余命に関する研究では、性別や年齢を問わず、歩行スピードが速いほど寿命が長く、遅いほど寿命が短くなるということが明らかになっています(JAMA. 2011; 305: 50-58)。
筋力の低下、感覚の障害、バランスの障害など、歩きにくくなった原因をみつけることが肝心ですので、まず脳神経内科医に相談することをおすすめします。
代表疾患
脳梗塞、パーキンソン病、脊髄小脳変性症、頸椎症性脊髄症、末梢神経障害、筋炎など
“つつみメモ”
ポイント1:起立位の観察と検査
「歩いて」もらう前に、まずは「起立できる」かを確認します。立てないこと自体が重要な所見です。
- 姿勢の観察:Wernicke-Mann肢位(片麻痺)や体幹の傾き、腰椎の前弯などをチェック。
- 片足立ち:5秒以上立てるか?(支持筋力低下、運動失調の評価)
- つま先立ち・踵立ち:下腿遠位筋の脱力をチェック。
- しゃがみこみ試験:下肢近位筋の筋力低下を評価(Gowers徴候に注意!)。
- ロンベルク試験:深部感覚障害の評価。
- マン試験:小脳失調、前庭機能障害、深部感覚障害の評価(高齢者では転倒に注意!)
- 押し試験と引き試験:姿勢保持反射障害を評価(パーキンソン病や進行性核上性麻痺などの評価)。
ポイント2:歩行の観察7つのポイント
歩行観察では、以下の7点に注意します。
- 姿勢:前屈(パーキンソン病、圧迫骨折)、後屈(進行性核上性麻痺)、側屈の有無。
- 脚幅:広がる(小脳失調、正常圧水頭症)、狭くなる(痙性対麻痺)
- 歩行開始:すくみ足の有無(パーキンソン病、進行性核上性麻痺)。
- 歩幅:狭くなる(パーキンソン病)。
- 膝:屈曲・伸展の可否。
- 足底の上がり:上がりすぎ(腓骨神経麻痺)、上がらない(パーキンソン病、脳血管性パーキンソニズム、正常圧水頭症)。
- 腕の動き:振りが小さくなる(パーキンソン病初期)、左右に広がる(小脳失調)。
ポイント3:8つの特有な異常歩行
一目で「おかしい」とわかる異常歩行を知っておくと、診断の助けになります。
- 痙性歩行:痙性片麻痺歩行(分回し歩行)、痙性対麻痺歩行(はさみ足歩行)。
- 運動失調性歩行:開脚歩行、踵打ち歩行。
- 動揺性歩行:別名Waddling gait。体幹を左右に振り、不安定な歩行。
- パーキンソン歩行:前傾姿勢、小刻み歩行、すくみ足、加速歩行。
- 小刻み歩行:前頭葉病変で、前傾姿勢で小刻みに足を滑らせる歩行。
- 鶏歩:別名Steppage gait。下垂足で膝を高く上げて歩く歩行。
- 間欠性跛行:歩行で下肢痛が出現し休息で軽快する状態。血管性、非血管性(腰部脊柱管狭窄症)が原因として挙げられる。
- ヒステリー性歩行:非特異的な異常歩行、症状の変動性がある。奇妙・誇張・変動性がある歩行障害とも言い換えられる。